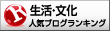思いやりと自発性で経済を支える社会
-最終更新日:2010年8月7日(土)-
「人のつながり」もそうですが、今回は直接的に経済活動と関係のない人間の営みについて考えてみたいと思います。
例えば、近所の人との親密なつながりで、必要なときに「お醤油」を貸してあげたとします。そのときに、自分の家の醤油が10円分減ったとします。このとき、相手の家は、10円分の醤油の分だけ得をしたということになります。経済学的な考え方だと、財の移動という観点からこのように説明できます。このときの交換にかかるコストは、近所づきあいでの言葉や表情のやり取りという労力だけです。これは経済的に浪費がないものとして扱われます。
しかし、それだけでこの人間の行為が説明できるでしょうか。この過程で、人間の信頼関係の交換が行われています。まず、助けられたほうが、「助かった」という心情的な喜びを感じます。助けた方も、「助けてあげた」という達成感を報酬として感じているかもしれません。さらに、これが繰り返されて信頼関係が形成されると、相互に報酬を受ける関係が形成されます。困ったときに助け合うようになるからです。これを「互酬性」といいます。
現在の日本で問題なのは、このようなコミュニケーションに労力が割かれることに対して、個人が反発してしまうことです。モノが豊かなので、店で買えばすんでしまうからです。さすがにこの時代には、10円分の醤油を近所に借りるという行為は成立しないかもしれません。しかし、この信頼関係こそが、単純な経済学的な財の移動以上の人間の豊かさを生み出します。人間は、経済的に豊かになることも幸せの重要な指標の一つです。しかし、このような直接的に経済活動によらない信頼関係も、人間が忘れてはならない幸せの指標の一つです。
このように、経済活動の後ろに隠れた、さまざまな人間の営みというものがあります。そういったものが経済活動やその成長の下支えをしているということを忘れてはいけません。
「シャドウワーク(shadow work)」という呼び方をされることもあります。代表的なものは「勉強」や「家事」などです。
「勉強」は高い集中力と頭の労働が必要です。しかし、それ自体に報酬は一切ありません。しかも、専門的な勉強を行うとなると、相当時間がかかります。言い換えるなら、その時間だけ労働したら儲かる可能性があるのに、なぜ「勉強」をするか、です。それは、未来に対する報酬を勝ち取るためです。受験勉強に勝とうとするのも、資格試験に合格するのも、それが大きな目的の一つです。人間は、義務教育だけで9年間勉強します。それだけ勉強の時間を費やして、世の中の役に立ったり、世界的な技術を開発する専門家になれるのです。私が言いたいのは、経済的に報酬がない「勉強」を人間はお金を払ってまで本気になってやるということです。
「家事」もシャドウワークの代表的なものです。ある家族3人分の夕食の材料を850円で買ってきたとします。調理にかかった水道光熱費が50円とします。では、この食事は一人当たりいくらでしょうか。誰でもお分かりのように、(850+50)÷3=300 円です。人件費はありません。お母さんがどんなにプロ級のおいしい料理をつくったとしても、お給料が支払われるわけではありません。他にも、洗濯、アイロンがけ、掃除、布団干し… やろうと思ったらいくらでもあります。しかも、丁寧に行えば行うだけ、家族が充実してきます。この、家庭で行われる経済活動でない人間の営みが、働くお父さんの英気を養って、子どもの明日を育てます。
現在の厳しい財政状況の国にあって、何が国民を豊かにさせ、経済を下支えするかといえば、このような経済活動でない営みの充実です。それ自体報酬があるわけではありません。しかし、これらのことに労力をかければかけるだけ、人間が育ちますし、社会が底上げされます。地域とのコミュニケーションの深化も、これまで述べてきた「互酬性」という観点から、地域に住む住民に活力を与えることにつながります。
現代は、経済活動に直接関与しない無駄な行為をできるだけしないほうが格好いいという風潮さえあります。しかし、自分たちで最大限努力して栄光ある未来を勝ち取る、そのような意識をもった主体が自由主義経済にあるべき個人の本来の姿です。資本主義の勃興期に、このテーマの本が多く出版されています。また、「自助(self-help)」とは、その個人のあるべき意識を表現したものの一つです。この考え方を最初に考え出した本によると、「天は自ら助けるものを助く (God helps those who help themselves.)」と表現しています。すなわち、「努力をすれば必ず報われる」という考え方です。経済の自由主義を最初にとなえたアダム・スミスに強く影響されています。
最後に何度も言いますが、これらのものに報酬はありません。労力もそれなりにかかります。それでも、長期的な視野でこれらのものが充実した地域・社会・家庭を作れば、日本の未来は明るいといえます。これらのことに力を入れた人に栄誉が授けられる社会であってほしいなと思います。
【記事の参考図書の追加 2010年10月7日(木)】
-----------------------------------------------------------------------------------
当ブログは「人気ブログランキング」を応援しております。問題の認知と被害者の救済のためにぜひクリックをお願いいたします。
![人気ブログランキングへ]()
-最終更新日:2010年8月7日(土)-
「人のつながり」もそうですが、今回は直接的に経済活動と関係のない人間の営みについて考えてみたいと思います。
例えば、近所の人との親密なつながりで、必要なときに「お醤油」を貸してあげたとします。そのときに、自分の家の醤油が10円分減ったとします。このとき、相手の家は、10円分の醤油の分だけ得をしたということになります。経済学的な考え方だと、財の移動という観点からこのように説明できます。このときの交換にかかるコストは、近所づきあいでの言葉や表情のやり取りという労力だけです。これは経済的に浪費がないものとして扱われます。
しかし、それだけでこの人間の行為が説明できるでしょうか。この過程で、人間の信頼関係の交換が行われています。まず、助けられたほうが、「助かった」という心情的な喜びを感じます。助けた方も、「助けてあげた」という達成感を報酬として感じているかもしれません。さらに、これが繰り返されて信頼関係が形成されると、相互に報酬を受ける関係が形成されます。困ったときに助け合うようになるからです。これを「互酬性」といいます。
現在の日本で問題なのは、このようなコミュニケーションに労力が割かれることに対して、個人が反発してしまうことです。モノが豊かなので、店で買えばすんでしまうからです。さすがにこの時代には、10円分の醤油を近所に借りるという行為は成立しないかもしれません。しかし、この信頼関係こそが、単純な経済学的な財の移動以上の人間の豊かさを生み出します。人間は、経済的に豊かになることも幸せの重要な指標の一つです。しかし、このような直接的に経済活動によらない信頼関係も、人間が忘れてはならない幸せの指標の一つです。
このように、経済活動の後ろに隠れた、さまざまな人間の営みというものがあります。そういったものが経済活動やその成長の下支えをしているということを忘れてはいけません。
「シャドウワーク(shadow work)」という呼び方をされることもあります。代表的なものは「勉強」や「家事」などです。
「勉強」は高い集中力と頭の労働が必要です。しかし、それ自体に報酬は一切ありません。しかも、専門的な勉強を行うとなると、相当時間がかかります。言い換えるなら、その時間だけ労働したら儲かる可能性があるのに、なぜ「勉強」をするか、です。それは、未来に対する報酬を勝ち取るためです。受験勉強に勝とうとするのも、資格試験に合格するのも、それが大きな目的の一つです。人間は、義務教育だけで9年間勉強します。それだけ勉強の時間を費やして、世の中の役に立ったり、世界的な技術を開発する専門家になれるのです。私が言いたいのは、経済的に報酬がない「勉強」を人間はお金を払ってまで本気になってやるということです。
「家事」もシャドウワークの代表的なものです。ある家族3人分の夕食の材料を850円で買ってきたとします。調理にかかった水道光熱費が50円とします。では、この食事は一人当たりいくらでしょうか。誰でもお分かりのように、(850+50)÷3=300 円です。人件費はありません。お母さんがどんなにプロ級のおいしい料理をつくったとしても、お給料が支払われるわけではありません。他にも、洗濯、アイロンがけ、掃除、布団干し… やろうと思ったらいくらでもあります。しかも、丁寧に行えば行うだけ、家族が充実してきます。この、家庭で行われる経済活動でない人間の営みが、働くお父さんの英気を養って、子どもの明日を育てます。
現在の厳しい財政状況の国にあって、何が国民を豊かにさせ、経済を下支えするかといえば、このような経済活動でない営みの充実です。それ自体報酬があるわけではありません。しかし、これらのことに労力をかければかけるだけ、人間が育ちますし、社会が底上げされます。地域とのコミュニケーションの深化も、これまで述べてきた「互酬性」という観点から、地域に住む住民に活力を与えることにつながります。
現代は、経済活動に直接関与しない無駄な行為をできるだけしないほうが格好いいという風潮さえあります。しかし、自分たちで最大限努力して栄光ある未来を勝ち取る、そのような意識をもった主体が自由主義経済にあるべき個人の本来の姿です。資本主義の勃興期に、このテーマの本が多く出版されています。また、「自助(self-help)」とは、その個人のあるべき意識を表現したものの一つです。この考え方を最初に考え出した本によると、「天は自ら助けるものを助く (God helps those who help themselves.)」と表現しています。すなわち、「努力をすれば必ず報われる」という考え方です。経済の自由主義を最初にとなえたアダム・スミスに強く影響されています。
最後に何度も言いますが、これらのものに報酬はありません。労力もそれなりにかかります。それでも、長期的な視野でこれらのものが充実した地域・社会・家庭を作れば、日本の未来は明るいといえます。これらのことに力を入れた人に栄誉が授けられる社会であってほしいなと思います。
【記事の参考図書の追加 2010年10月7日(木)】
 | シャドウ・ワーク―生活のあり方を問う (岩波現代文庫) (2006/09) I. イリイチ 商品詳細を見る |
-----------------------------------------------------------------------------------
当ブログは「人気ブログランキング」を応援しております。問題の認知と被害者の救済のためにぜひクリックをお願いいたします。